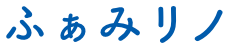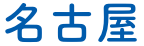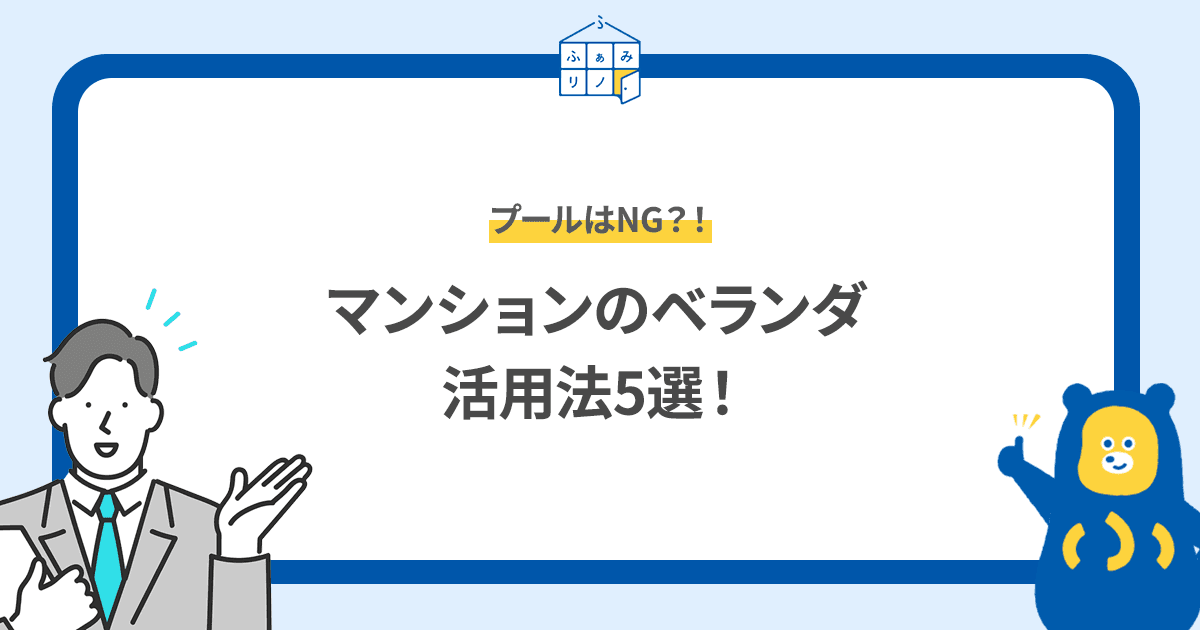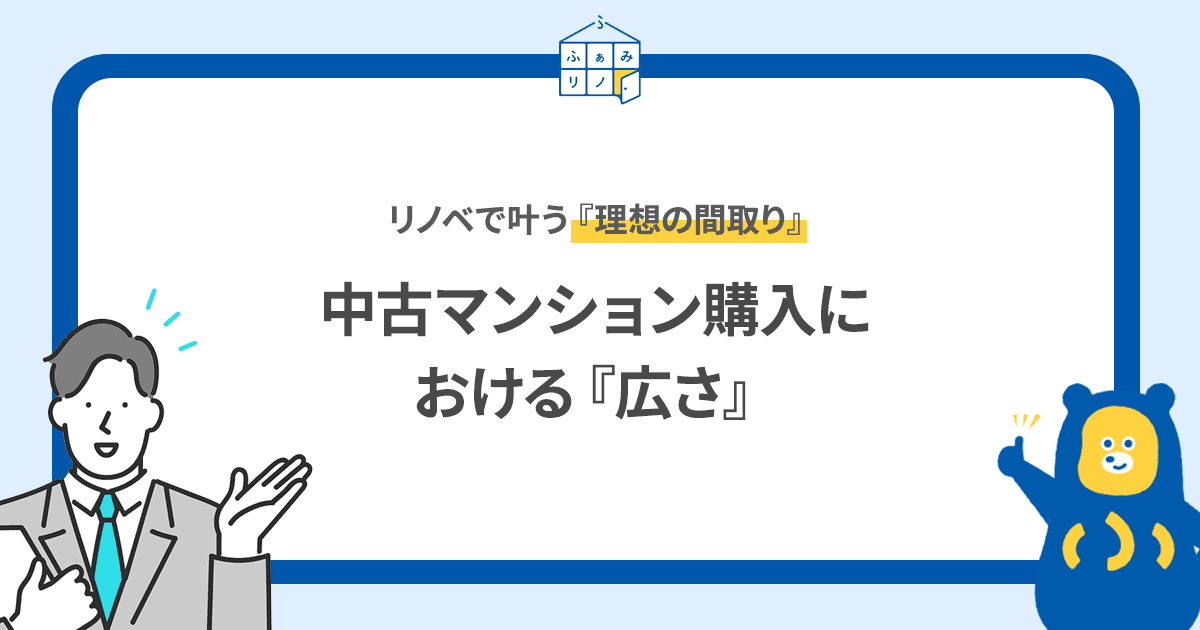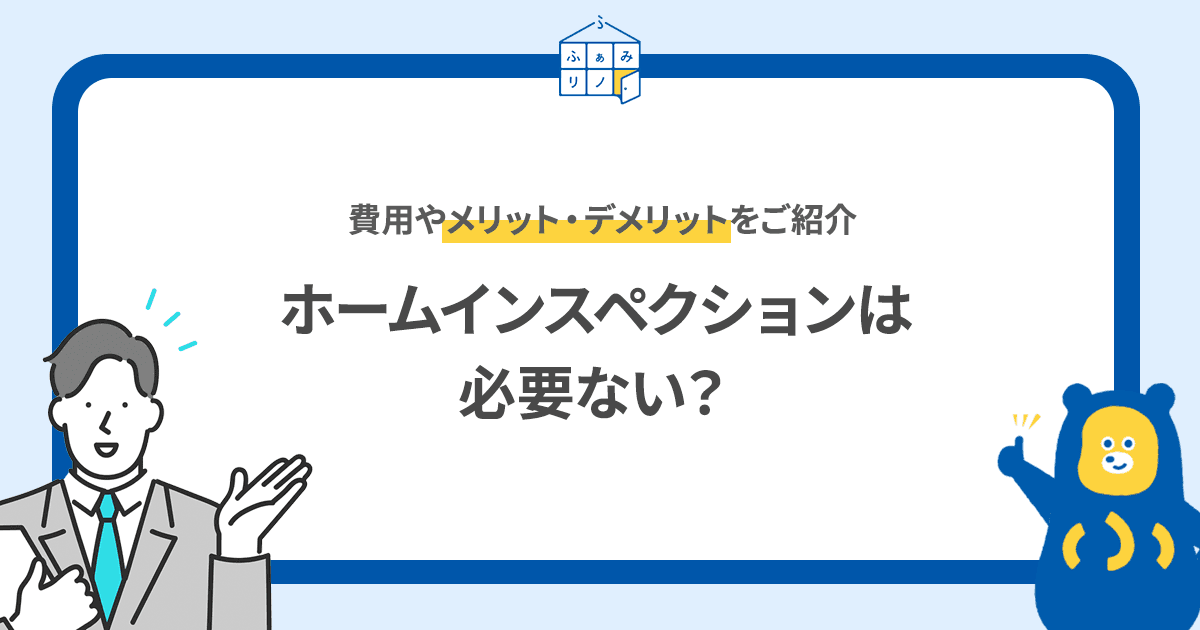床材の種類と機能8選!メリット・デメリットもご紹介
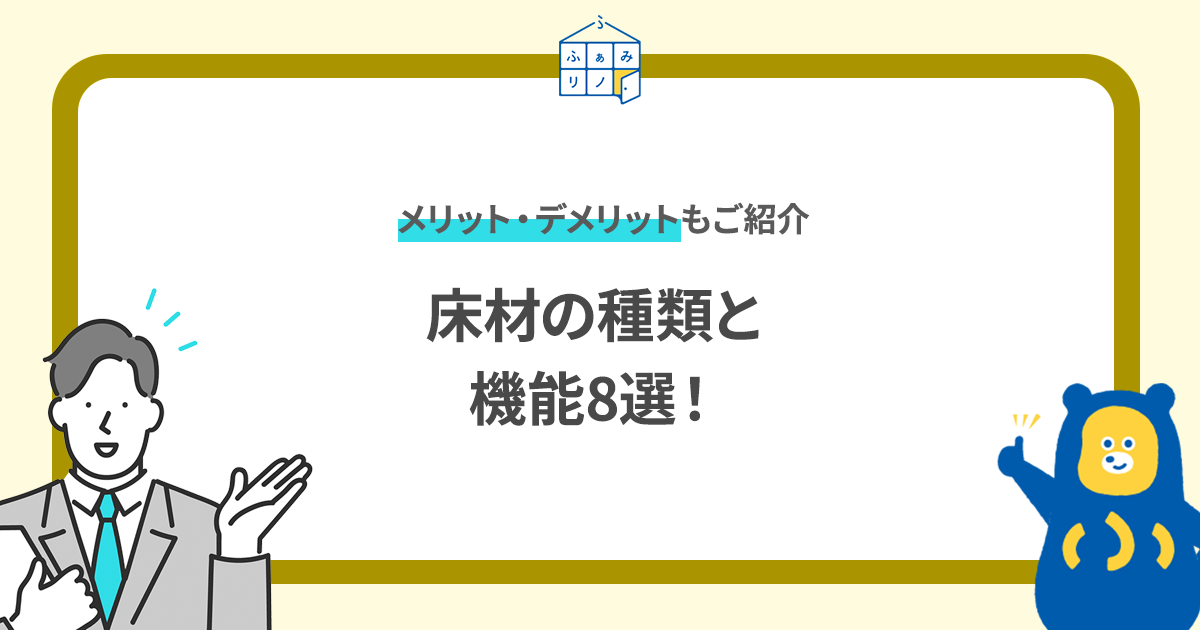


「中古住宅を買って素敵にリフォームしたいから、床材の種類とか機能はどんなものがあるんだろう?」
そんな風にお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんね。
最近はデザイン・機能ともにいろいろな種類の床材が出ていて迷ってしまうこともあるかもしれません。
そこで今回は床材の種類とその機能について解説していきます。
お好みの床材と出会うためのヒントにしてくださいね。
床材の種類とそれぞれの機能

まず床材にはどのような種類があり、それぞれどのような機能や特徴があるのか?を見ていきましょう。
床材には
・フローリング
・クッションフロア
・フロアタイル
・カーペット
・畳
・リノリウム
・天然石やタイル
・コルク
など8種類ほどあります。
それぞれの特徴をメリット・デメリットと合わせて紹介していきます。
フローリング
まずは床材と言えば誰もが思い浮かべるといっても過言ではないフローリングから。
フローリングには大きく分けて
✓無垢材フローリング(杉やひのきなどの天然素材)
✓複合フローリング(合板い木目をプリントしたシートを張り合わせたもの)
の2種類がありますよ。
特に無垢材は足ざわりがとても心地いいので、リビングなどでの使用におすすめです。
フローリングのメリット
インテリアになじむ
フローリングの一番のメリットはその見た目とも言えるでしょう。
木目は主張しすぎず、温かい雰囲気を作り出してくれるので、どのようなインテリアにもマッチしてくれるでしょう。
無垢・複合タイプともに家具との相性を考えて、素材や色を考えたいところですね。
無垢は強い
フローリングの中でも、特に無垢材は傷がつきにくく耐水性もあるので丈夫です。
お気に入りの床材が徐々になじんでいくのを楽しみながら、長い付き合いをしたいかたにおすすめですよ。
フローリングのデメリット
コストが高い
このあと紹介するポリ塩化ビニル製のクッションシートなどに比べると、無垢材・複合フローリングともにコストは高くなりがちです。
コストが気になるかたは、「リビングはフローリングだけどキッチンはクッションシートにする」などこだわりの部分のみに使用するなど、他の床材と組み合わせるのもおすすめです。
無垢はメンテナンスが大変
肌触りのよさが魅力の無垢材ですが、天然素材なだけに
・ワックスがけ
・板の反りに注意
・取れないよごれはやすりがけ
などなど定期的なメンテナンスが必要になります。
無垢材を採用する場合には、そのメンテナンスも楽しむくらいの気持ちが重要です。
長持ちする無垢材は、お手入れするほど愛着がわいてきますからね。
クッションフロア

クッションフロアはクッション性に優れたシートのこと。多くの場合ポリ塩化ビニルなどで作られています。
木目や石目など、デザインが豊富で好みに合わせて、選ぶことができますよ。
防水性も高いので、キッチンや洗面所などにおすすめです。
クッションフロアのメリット
コストが安い
クッションフロアは、デザインによってはフローリングのような木目調の暖かさを味わえるにもかかわらず、コストが抑えられるのが魅力です。
部屋の雰囲気を保ちながらも、価格を抑えたい場合におすすめです。
防水・防汚性が高い
クッションフロアはポリ塩化ビニルでできていることが多いため、防水性や防汚性に優れています。
水をこぼしてしまってもしみこむことなくササっと拭き取れますし、表面がさらっとしているので、汚れがつきにくく取れやすいです。
洗い物で水を使ったり、油汚れが気になるキッチンにおすすめの理由がここにあります。
選択肢が豊富
最近はプリント技術も高くなっているため、一見フローリングと見間違えるくらいのクオリティのものもありますよ。
クッションフロアのデザインにはフローリングだけではなくて、大理石調やタイル風などたくさん揃ってます。
自分好みのデザインをインテリアに合わせて、選ぶ楽しみがありますね。
クッションフロアのデメリット
家具のあとが残りやすい
クッションフロアは名前の通り、クッション性が抜群です。
そのため長時間置いてある家具などのあとがつきやすいのが難点です。
模様替えを頻繁に楽しむような方は注意が必要でしょう。
質感がチープ
本物のような質感が楽しめるようになってきたとはいえ、やはり実際に歩いてみたり近くでみてみると、ビニルのチープさが気になることもあるでしょう。
ただしこういった質はメーカーによって大きく異なります。
気になるクッションフロアがあった場合には実際にサンプルを取り寄せてみることをおすすめします。
熱に弱い
クッションフロアはポリ塩化ビニル性なので高熱に弱いです。
アイロンなどを床に置いてしまわないように注意しましょう。
誤って倒れると溶ける、焦げるなどで床に跡がついてしまいます。
フロアタイル
フロアタイルも木目調や石目などをプリントしたポリ塩化ビニルでできたシートのことです。
さきほど紹介したクッションフロアとの違いは、大きなシートではなくタイル状になっていること。
クッションフロアのようなクッション性はありませんが、土足で利用できるなど耐久性の高いものもありますよ。
クッションフロア同様防水性が高いのでキッチンや洗面所などにおすすめです。
クッションフロアのメリット・デメリットと似ているので、ここはサクッと解説していきます。
フロアタイルのメリット
・よりリアルな質感が楽しめる
・耐久性がある
フロアタイルはサイズが小さいこともあり、クッションシートよりも施工がしやすく、よりリアルな質感が楽しめると言われています。
クッションフロアのようなクッション性は少ないですが、その分頑丈にできており、耐久性に優れていますよ。
クッションフロアのデメリット
・塩化ビニル製は熱に弱い
・クッション性がない
クッションフロアのデメリット同様、フロアタイルも熱に弱いです。アイロンなどの使用はくれぐれもご注意を!
カーペット

裸足で歩いてもふかふかの肌触りが楽しめるのが特徴のカーペット。
素材は大きく2つ。
コットン・シルク・ウールなどの「天然素材」と、ナイロンアクリルなどの「化学繊維」に分けられます。
また、カーペットの種類には
・パイルの先端を切りそろえた肌触りのよい「カットパイル」
・パイルがループ状になっている耐久性の高い「ループパイル」
・どちらのいい点も兼ね備えている「カット&ループパイル」
など3種類がありますよ。
裸足でゆったりすごせるので、寝室などにおすすめです。
カーペットのメリット
肌触りがよい
なんといってもカーペットの魅力はその肌触りのよさではないでしょうか?
フワフワとした感触を足先から感じると、全身リラックスしてしまいますよね。
滑りにくく柔らかいので、お子さんが走り回ったり寝転んでいても安心です。
クッション性が高い
カーペットはたくさんのパイルが集まって完成してますので、クッション性が高いです。
フローリングよりは防音効果もありますので、お子さんの活発な動きにも対応してくれます。
カーペットのデメリット
メンテナンスが大変
カーペットの場合は、拭きやすいフローリングと違い日々の掃除やメンテナンスが大変です。
スチーム式の掃除機でのお手入れや業者に頼むなど、定期的なメンテナンスをして衛生管理をする必要があるでしょう。
水分との相性が悪い
カーペットはパイルでできているので、水分を吸収してしまいます。
ただの水ならまだいいですが、ブドウジュースや醤油など、色の濃い水分の取り扱いには十分注意したいところです。
ダニなどが吸着しやすい
ふわふわの毛足はダニたちも心地よく過ごせます。
また日々のメンテナンスが難しいことから、ハウスダストなどにも注意が必要です。
畳

日本人なら癒されること間違いなし!イグサでつくられた床材の畳です。
ちょっと和の雰囲気を強くしてしまいがちで、敬遠されてしまうかもしれませんね。
ですが、最近は正方形やふちなしのタイプなど、現代のインテリアにもマッチするモダンなものも増えています。
ごろりとくつろぐリビングの一角や寝室におすすめです。
畳のメリット
肌触りがよい
なんといっても畳のメリットはごろりと横になっても気にならない質感や肌触りではないでしょうか?
フローリングではマットが敷いていないとなかなかごろりとしにくいですが、畳ならそのまま寝転んでも痛くないですよね。
またイグサは冬でもひんやりすることはないので、どんな季節でも快適な使い心地が楽しめます。
クッション性が高い
畳はクッション性も高いので、物を落としたりお子さんが転んだりしても安心です。
お子さんが小さなうちはリビングの一角に畳の部屋をもうけて、お子さんの遊ぶスペースにしてもいいでしょう。
バタバタと動き回ってもフローリングよりは下の階に響きにくく、お子さんを思いっきり遊ばせてあげられますね。
インテリアに凝れる
最近の畳はへりがなかったり、正方形のものがあったり、色の選択肢が多かったりとインテリアの一部としても楽しめます。
こうしたインテリア性の高い畳は、洋風の住宅にもマッチしてくれますよ。
畳のデメリット
メンテナンスが大変
畳を長く使うためには裏返しや表返しなどのメンテナンスが必要です。
メンテナンスをするためには、一度家具をすべてどかすなどの手間が必要になりますので、注意が必要です。
最近はこういったメンテナンスをなるべく少なくできるような商品もでていますので、リフォーム会社などに相談してみましょう。
ダニなどが吸着しやすい
カーペット同様、畳もフローリングに比べると凸凹が多く、ダニやほこりを吸着しやすいです。
こまめに掃除機をかけたり、拭き掃除をするなど、日々のお手入れも大切です。
日焼けや家具のあとがつきやすい
畳は長年つかっていると、日に当たっていた部分が変色してしまったり、家具の跡がつきやすかったりします。
さきほど紹介した「裏返し」「表返し」などのメンテナンスで対応もできますが、日焼けや家具の跡が付きにくい配慮が必要です。
どうしても家具をおきたい場合には、部屋の隅だけフローリングにしておくなどの方法も有効ですよ。
リノリウム
ここから先はまだあまり一般的ではない床材の解説になりますので、サクッと紹介していきますね。
従来の床材とは違うものを探しの方は、参考にしてください。
リノリウムとは木紛・コルク紛などの天然素材から作られていて、テーブルの天板など家具の仕上げ材としてもつかわれています。
〇天然素材なので有害物質が発生しにくい
〇燃えにくい
〇滑りにくく歩きやすい
〇耐久性に優れている
などのメリットがありますが、
×匂いが気になる可能性(原料の一つ亜麻仁油独特のにおいがある)
×価格が高い
×施工できる業者が限られる
などのデメリットも考えられます。
もともと病院などの施設で使われることの多かったリノリウムですが、その使い勝手のよさから、最近は一般家庭での使用にも注目されています。
燃えにくく・滑りにくいという特性があるので、キッチンや子ども部屋などにおすすめです。
石やタイル
ここで紹介するのは大理石などの天然の石や磁器質セラミック・ガラスなどのことで、ポリ塩化ビニル以外のタイルのことを差します。
本物の質感を味わえるので、高級感を出したいときにおすすめ。
〇見た目がゴージャス
〇汚れに強い
〇タイルは床暖房に適している
〇天然素材なので安心
〇劣化がおこりにくい
などのメリットがありますが、
×高い
×タイルはは割れやすい
×クッション性がない
×冬冷たい
などのデメリットが考えられるでしょう。
使う場所や範囲などを考えて、上手に取り入れたいところです。
コルク
「コルク」というとワインの栓を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実は床材にもなるんです。
コルクの「防水・防音・防炎・調湿」という特徴は
✓キッチン
✓洗面所
✓子ども部屋
など幅広い場面で使用できますよ。
〇リサイクル可能でエコ
〇防音性がいい
〇滑りにくい
というメリットと
×色あせる
×跡が付きやすい
×取り扱える業者が少ない
というデメリットが考えられるでしょう。
床材を選ぶときの注意点
ここでは、床材を選ぶときに注意したいポイントを紹介していきます。
床材を選ぶときには「部屋の目的に合わせる」「必ずサンプルを取り寄せる」ということに気を付けましょう。
部屋の目的に合わせる
床材を選ぶときには、
「まだ子どもが小さいので、畳の部屋を用意しよう」
「大人だけの世帯なので高級感も取り入れたい」
「寝室は落ち着けるカーペットがいい」
など、自分がその部屋を実際に使っているところをイメージして、採用するといいでしょう。
単に「見た目がかっこいいから」「価格が安かったから」などで安易に選択してしまうと、暮らしにくくなってしまうこともあるので、気を付けてくださいね。
必ずサンプルを取り寄せる
いくつか候補がきまったら、必ず実際のサンプルを取り寄せるようにしましょう。
画像だけでは実際のものと色味が違っていたり、質感が全く違う可能性もあります。
メーカーやリフォーム会社にお願いして、実物をチェックするようにしましょう。
こういったひと手間で、出来上がった後の「こんなはずじゃなかった…」を防げますね。
まとめ

以上、床材の種類と選び方について解説してきました。
床材には
・フローリング
・クッションフロア
・フロアタイル
・カーペット
・畳
・リノリウム
・天然石やタイル
・コルク
の8種類がありました。
一般的には
・フローリング
・クッションフロア
・フロアタイル
・カーペット
・畳
が使われることが多く
・リノリウム
・天然石やタイル
・コルク
は、まだあまり一般的ではないかもしれません。なにか新しい床材を検討している人におすすめです。
また、床材を選ぶ際には必ずサンプルを取り寄せて、実物の質感や色味を確認するようにしましょう。
部屋の使用目的や予算に合わせて、お気に入りのものを探してみてくださいね。